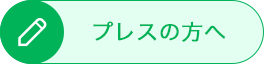セミナーA「50thプレミアムセミナー」
参加無料 事前登録あり
会場
東8ホール
内容
| 日時 | 講師・登壇者 |
|---|---|
|
9月27日(水)
手話通訳あり |
多世代交流・コミュニティケアを通じた住民共創のまちづくり
地域共生社会の実現に向け誰もが暮らしやすいまちづくりを実現していくためには、あらゆるステークホルダーが地域全体で連携し協働しながら一層の実践を深めていくことが必要であり、とくに知識や技術、資源を有する民間事業者等と自治体とが連携してまちづくりを実践していく取組みも重要です。 神奈川県藤沢市におけるパートナー企業と自治体との官民一体の共同プロジェクト「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」について、福祉の視点の事業紹介も含め先進事例を紹介します。 |
|
|
|
| 9月28日(木) 10:30~11:30 |
利用者を大切にした福祉サービスと質の向上の実現
上記テーマに添い、利用者の権利擁護等に配慮した福祉施設・事業所における支援・サービスの向上と、その質を高めるために人材をどう育てていくかについて、それぞれの分野の立場から取り組みの現状や留意点、展望等についてスピーチいただきます。 |
|
<ここがポイント!> 障害福祉施設・事業所において「新人職員が虐待に気づいたら?」「どこまでが許される支援か、許されない虐待か」「さまざまな生活場面において、代行決定ではなく、本人と意思決定権限者が共同して決定ができているか」など、福祉事業に従事する職員のアイデンティティー面も含め、掘り下げて具体的に考察します。 |
|
|
<ここがポイント> 児童福祉施設における「年齢ではなく人として遇する(尊重)こと」から生まれる専門的役割と使命について、「スタッフにも帰属感が持てる」ようなチームづくり、「スタッフ一人ひとりがライフステージを描ける環境づくり」のための人材育成イメージとレベルアップ等について、掘り下げて考察します。 |
|
|
<ここがポイント> 介護福祉事業分野において、身体拘束のない福祉現場づくりのため施設内研修で使用している事例を紹介し、「緊急やむを得ない場合」等の徹底整理を行うとともに、国の調査では虐待の発生要因が職員の「教育・知識・介護技術等に関する問題」に発生する割合が最多である事実を受け止め、職員の疲弊や離職につながらない現場づくりについて考察します。 |
|
| 9月28日(木) 15:30~16:30 |
海外進出をすすめる福祉機器企業の展開例 グローバルな視点をもって海外での事業展開を図りたいと考えている日本の福祉機器開発事業者等に役立つ、国の支援策紹介ならびに実際の展開例を報告します。 |
|
■第一部:基調講演
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 室長補佐 南須原 美恵 氏 <ここがポイント> 同省における日本の福祉機器の海外展開支援施策について、ロボット介護機器産業関連の施策や海外の概況、海外展開上の課題と支援事業の内容等の説明がなされます。さらにそれを受け、下記2社による福祉機器の海外進出を考える際の具体的な実例報告へとつながっていきます。
■第二部:日本の福祉機器開発企業2社からの海外事業展開取り組み報告  トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 代表取締役 中西 敦士 氏
<ここがポイント> 2022年4月に介護保険適用福祉用具に指定された排泄予測デバイスD Free開発企業からみた世界市場規模と世界の関心度、米国での実績・検証・認証例、なぜ米国の在宅介護領域への進出か、現地関係者のコメント、医療機器認証や保険償還に向けた取り組み説明等が行われる予定です。
株式会社FUJI ロボットソリューション事業本部 技術開発部第5課 髙橋 立 氏
<ここがポイント> 移乗サポートロボットHugについて、海外の進出状況や海外展開のために必要とした取り組み(項目)の紹介、販売登録や規格認証をめぐっての米国での展開手続き例、規制に関連しての中国での販売登録のあり方紹介、日本企業が海外進出を図る場合のポイント紹介などが語られる予定です。 |